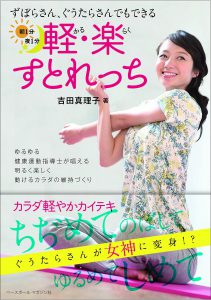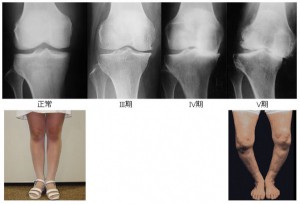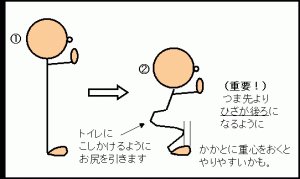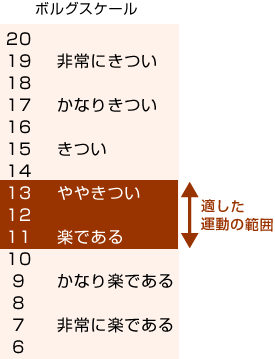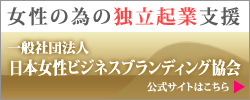加齢とひざの痛みの話 その3
♪Amazonで好評発売中です♪
ちぢめて・のばして・ゆるめて・しめて……、朝1分 夜1分でカラダが軽やかカイテキに生まれ変わる軽・楽(かる・らく)体操の決定版。日々の仕事に、日々の家事におわれるあまりカラダを動かすのが面倒だという“ぐうたらさん"でも簡単に取り組める。ゆるゆる健康運動指導士が唱える明るく楽しく、動けるカラダの維持づくりを紹介します。
著者:吉田 真理子(よしだ まりこ) ➡詳細はこちら
膝痛、腰痛、肩こり改善長生きフィットネス.com
シニアフィットネス・長生きストレッチの専門家
吉田真理子です。
膝の話の続きです。
筋力アップのトレーニングとストレッチは大事です。
しかし、すぐすぐに結果が出てこないのもじれったい話ですね。
そこで。
装具や用具説いたアイテムも上手に活用しましょう。
★膝の痛みには、サポーターの活用も有効★
膝の痛みを改善するには、
膝サポーターの活用もおすすめです。
膝サポーターは、
不安定になりがちな膝関節を固定して
痛みを軽減し、ズレた骨を正しい位置に
戻すことが期待できます。
さらに膝サポーターを装着することで、
膝の曲げ伸ばしや歩行が
しやすくなり、膝まわりの筋肉を
無理なく鍛えることができます。
ただし、サポーターならどれでも良い
というわけではありません。
運動選手が使うようなサポーターの場合、
肌に密着しすぎてムレやすくなります。
また、柔軟性が劣るものだと
動きが制限されて筋力の強化につながりません。
☆膝サポーターの選び方☆
運動用のサポーターと
普段使うサポーターは機能が違います。
固定力に優れていること。
両面テープ等で、ご自分の足に合わせてきっちりと巻けるもの。
ムレないこと。
長時間使用するものですので、
通気性の良い素材(メッシュ等)を使用し、
特にムレやすい膝の後ろ側がムレないように
なっているもの。
サポーター等を使うことで、
不安のないトレーニングで筋力をアップし
痛みの軽減や改善を目指してください。
まずは、できる範囲で始めてみましょう。
★インソールや衝撃吸収力の高い靴で膝への衝撃を緩和★
衝撃吸収力の高い靴を履くことでも
膝への負担を減らすことができます。
ちっぽけな事のように感じるかもしれませんが、
一歩一歩の積み重ねと考えると侮れませんよね。
合わせて、足底坂(インソール)を利用するのもいい方法です。
インソールは自分の体重を矯正力として利用する
膝痛対策用の靴の中敷です。
インソールで修正できるのは
下肢のバランス不良などにより、
膝関節の間にある軟骨がすり減ってしまい、
膝(主に内側)に痛みを生じた状態です。
足底面の角度をヒールウエッジパッドで調整し
、膝関節の角度を正常な状態に誘導して、
膝への負担を軽減。
3つのアーチを正常な状態にサポートし、
足の基本骨格を守り、痛みを軽減させます。
★冷やさない★
関節痛持ちの方は「寒い朝は特に膝が痛む」と
よく言います。
これは血行が悪くなるのと
関係が深いと言われています。
シニアの方は身体が一度冷えてしまうと
なかなか温まりにくいですので、
「冷やさない」という心構えが必要です。
★かかりつけドクターとは懇意にしておく★
普段診てもらっていて信頼できる整形外科医がいるのであれば、
その先生と長く付き合っていくのが良いと思います。
「痛い」と思ったら、「気のせい」「大丈夫」と我慢せずに
必ず信頼できる医師に相談をしましょう。
アドバイスをもらいながら、膝のケアを行ってください。
特にかかっている病院はないけれど膝が痛いと感じる、
何となく膝に違和感を覚えるとい時は、
加齢などによる膝の疾患を予防するため、
痛みや違和感の原因を突き詰めておくことが有用です。
また、先生から診断結果を聞くときは、
できる限り家族も一緒に話を聞くようにします。
自分一人だと、
どうしても自分に都合の良い診断結果は信じて、
都合の悪い結果は無視しがちになってしまいます。
今後、仮に治療となったら、家族の理解や協力は不可欠です。
客観的な立場で家族に話を聞いてもらい、
その内容を治療のサポートへと役立てていくことが、
回復への第一歩といえるでしょう。