
【地下室の階段プロローグ】
2020/9/27 14:55
以下の話はフィクションであり実在の人物などとは何ら関係あるものではありません。
「鬱は移るから、近づかないほうがいいよ。」
Kは少し距離を置きながら言い放った。
「なにそれ?シャレのつもり?」

午後2時の秋葉原。にぎわう電気街を抜けた、昭和の雰囲気漂う寂れた喫茶店。
この日、杏は初めてKと会った。
散々、グループメールや個人メッセージでやり取りをしていたから、旧知の仲のような感覚でいたが、約束の場に現れた男は杏の想像を超えた存在だった。
「煙草吸っていいかな。」許可を求めるというよりは、事後報告に近い口調。
「あ、どうぞ。」杏はKの細い指先が煙草のフイルムを破り、火をつける動作に吸い寄せられたまま、返事をかえす。
「俺さ、君で会う女の子3人目だよ。」
「ふーん。」
「ノンさん、キャンディ、そして君。」
2000年8月。まだ、携帯電話がi-modeと呼ばれる「ガラケー」がこれから主流になろうとしていた時代。杏と男は「30代だけが入れるメーリングリスト」で知り合った。
子どもがもうすぐ2歳になるのに、ダンナはいまだに就職する様子がない。仕方がなく杏は子供を保育園に預け、パートに出たがパート代は右から左へと保育園代に消える。なんのために働いているんだかわかりゃしない。
そんな杏の唯一の楽しみは、グループメールで語らうことだった。
「ノンさんは結構、病んでてさ。キャンディも病んでたこと、あるんだって。」
「ふーん。」
「俺、二人と寝たよ。」
「そう。」
何だろう、この男。
あさイチ「おはよう、死にたい。」と個人メッセージを送ってきておいて、女の話?
少し手が震えている。細長い指の根元近くでメンソールの煙草を挟み、時々わずかに左にゆがんだ口元に持っていく。
「で、君は?」
「別に。」

この後、杏は男のうつ病に振り回され、自らも闇(病み)の世界へ降りていく…のだが、
生々しく、読んでる側が息苦しくなり、大きく深呼吸して、思い切って読破する作品へと展開していくので、それはいずれまた。
#ふみサロ
#城村典子
#後藤勇人

このエッセイのBGMはこちら。https://amzn.to/42aARXM
- 投稿タグ
- ツレがうつになりまして, #ふみサロエッセイ, 地下室のメロディー







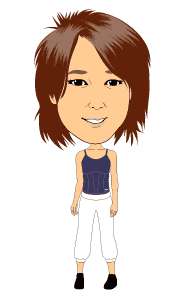




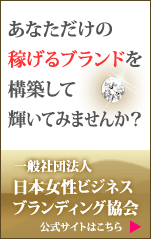

最近のコメント